QRコード決済
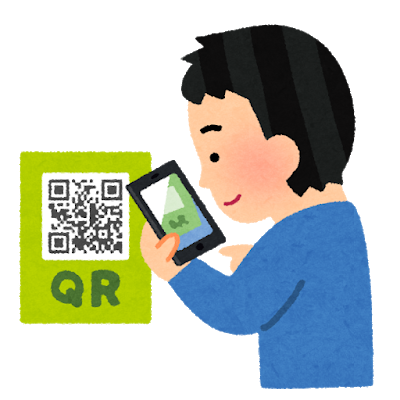
2018年2月、「三菱東京UFJ(現三菱UFJ)、三井住友、みずほの国内3メガバンクが、QRコード決済の規格統一に向けて連携へ」というニュースが話題になりました。QRコード決済市場への参入にあたり、規格の乱立を防ぎ、無駄なコストを削減するため連携を組み、必要なシステム投資等を共同で行う新会社の設立も検討しています。QRコード決済市場には、インターネット事業者からは楽天やLINEが、携帯キャリア事業者からはNTTドコモが参入を表明しています。
このQRコードという名前は、“クイック・レスポンス”に由来し、デンソー(現デンソーウェーブ)が部品工場などで使用するために、バーコードに替わる高速読み取りとして開発したものですが、特許は保有しているものの、権利行使はしないと明言したことから、世界中で利用されるコードに成長しました。
最近注目を集めているQRコード決済には、2通りの方法があります。1つは、スマホのディスプレイに表示したユーザーのQRコードを店舗側の端末で読み取って決済するもの。もう1つは、店舗側が提示したQRコードをユーザーがスマホのカメラで読み取って決済するもの。どちらも電子マネー決済に比べて店舗側の導入費用が格段に安く、また利用者も専用アプリを起動するだけで簡単に支払いが完了するというメリットがあります。クレジットカードが普及していない中国では、アリババグループのアリペイ等の利用が急速に拡大し、2018年3月からは日本でも正式なサービスを開始しています。
出典 経済産業省「キャッシュレス研究会の方向性:中国の決済サービス」(平成29年)
日本国内では既にSuica等のFeliCaインフラが展開し、また大手チェーン店を中心に国際規格として世界で利用されているTypeA/B方式の導入が検討されている中、なぜ今QRコード決済が注目されているのでしょうか。
そこには、依然として続いている中国人旅行者の「爆買い」、そして2020年の東京五輪に向けたキャッシュレス化の流れの中で、多くの小売店が興味を示し、世界の共通決済手段になりつつあるQRコード決済を導入しやすい土壌ができつつあるという背景があります。
QRコード決済をはじめ、IT技術を駆使した新しいサービスが次々と登場していますが、いずれ淘汰されて、便利で安全なサービスが残っていくことでしょう。5年後、10年後の私たちは一体どのような手段で支払いを行っているのか、今から楽しみでもあります。

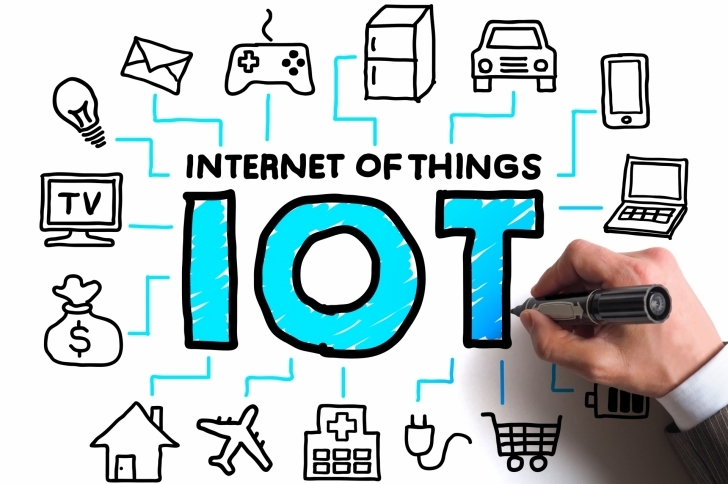
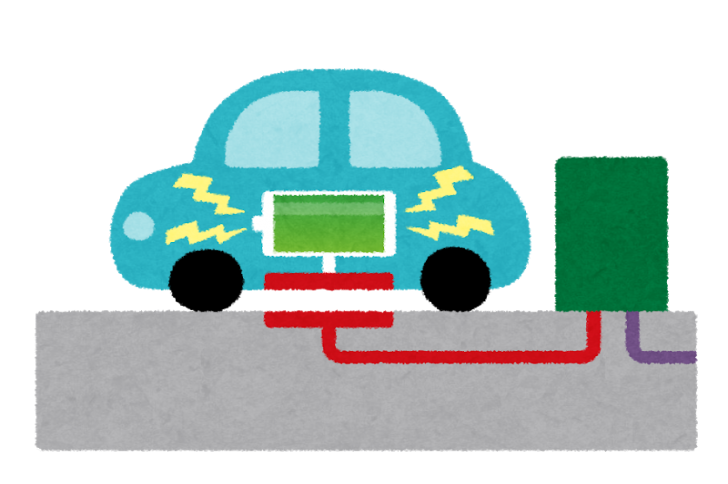

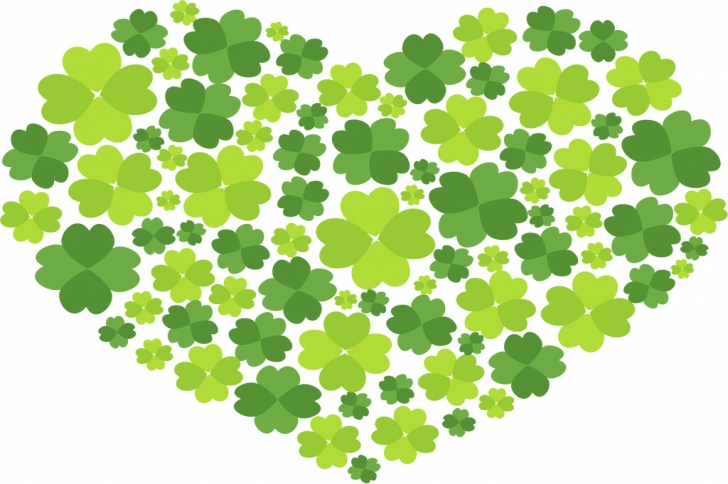
.JPG)

.JPG)