電波の種類

マックスウェルが電波(電磁波)の存在を予言(1864)し、マルコーニが無線通信の実験を行う(1894)までわずか30年でした。それから120年、 人類は電波を器用に使い、今では電波望遠鏡という観測ツールにも応用されています。さらに今や必需品となった携帯電話は電波なしでは話になりません。今回 はこの電波について「どんな種類があるのか」を考えてみたいと思います。
電波は「長波」「中波」「短波」と波長により区別されています。また「長波」と「短波」は頭に「超」「極超」などのような接頭語をつけて呼ばれますが、こ のなかで中波は主にラジオに使われている波長です。つまり中波ラジオと言うものですがNHK第1、NHK第2など多くの放送局で使われています。ここから 波長を短くしていくと短波、超短波になっていくわけで、極超短波の領域は携帯電話で使われており、この波長は10cm~1mあります。余談ですが、ひと昔 前の携帯電話はアンテナを伸ばして使っていたのに今ではそういう携帯は見かけなくなりました。それは使う電波の波長が短くなったためです。一般にアンテナ の長さは波長の偶数分の一が最も良いとされており、おもに1/4が採用されています。現在の携帯アンテナは本体内に収まる長さまで電波の波長が短くなった ということです。さらに波長が短く1cm~10cmになるとセンチメートル波といい高速道路のETCなどに使われています。そしてさらに 0.1mm~1mmになるといよいよ光の領域(赤色側)に近づきサブミリ波と呼ばれるようになり、最近では宇宙観測に使われ我々の住んでいる銀河系の構造 解明に大いに役立っています。直進する光では塵による妨害がありますが光よりも少し波長の長いサブミリ波では回析して届くため宇宙構造の解明にサブミリ波 が脚光を浴びているというわけです。
こんどは長い波長の方を見てみましょう。波長が1km~10kmの長波と呼ばれるものは電波時計に使われています。波は波長が長くなるに従って回析現象が 大きくなり障害物を透過する性質があります。電波時計の電波も高層ビルを透過し、くまなく届けなければなりません。波長が長くなると送信技術も難しくなり ますが、最も波長が長いものになると数万kmという電波もあります。ここまで来ると「水中は電波を通さない」という常識も破られ、潜水艦に情報を送る目的 に使われています。
マルコーニが数km離れたところに電波を送るのに成功してから120年。いまでは波長が0.1mmから数万kmまで目的に合わせて使う時代になりました。技術の進歩を波長という観点から見るのもおもしろいと思います。
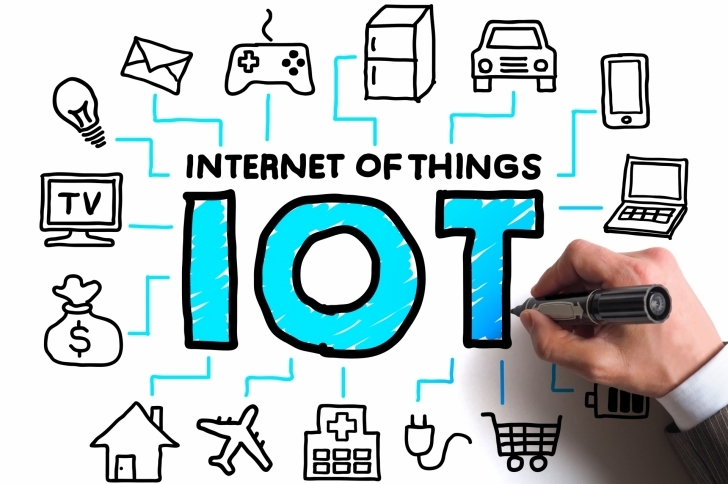
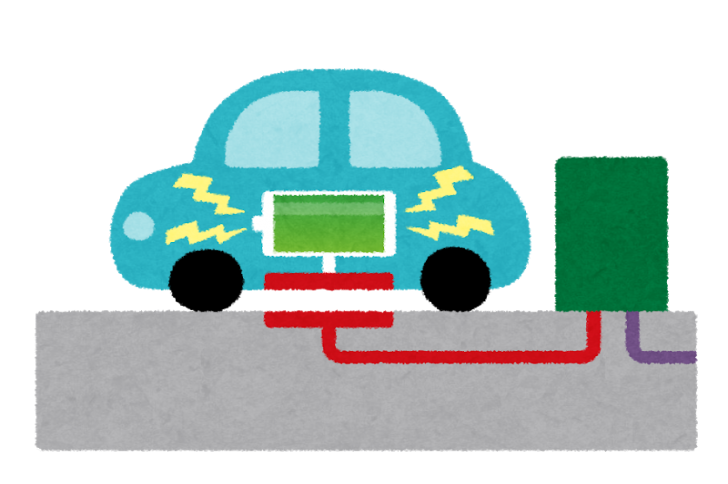
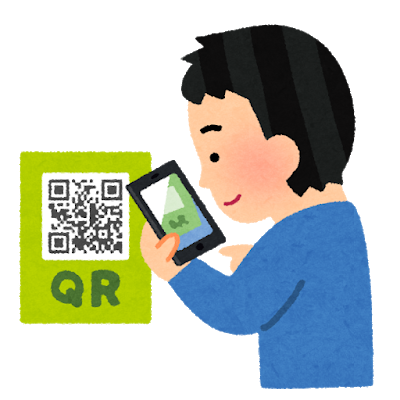
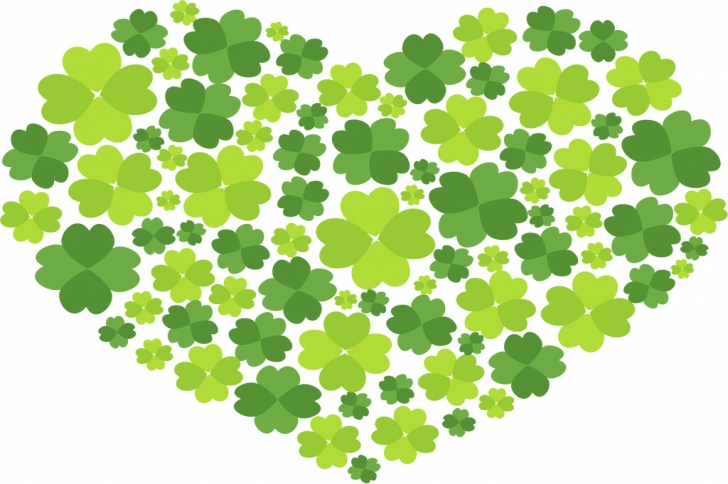
.JPG)

.JPG)